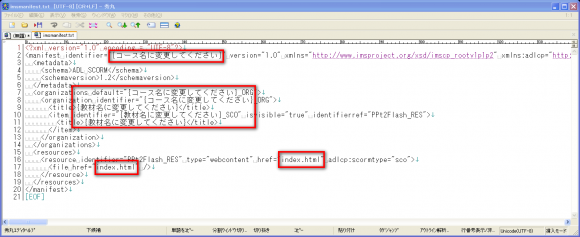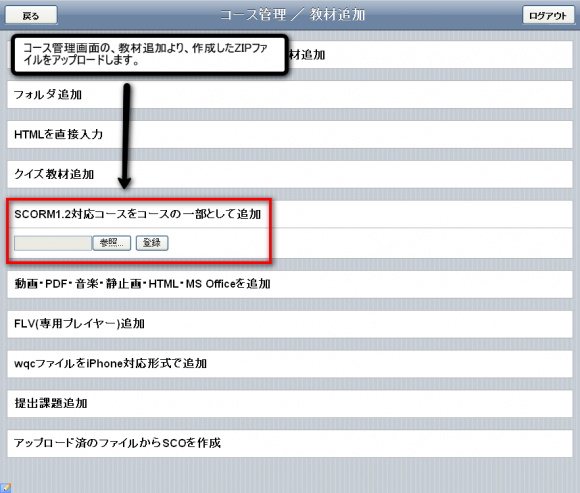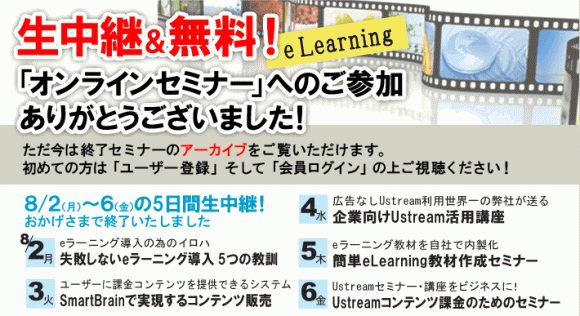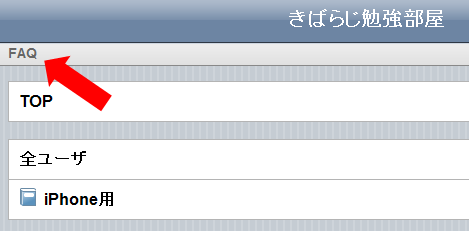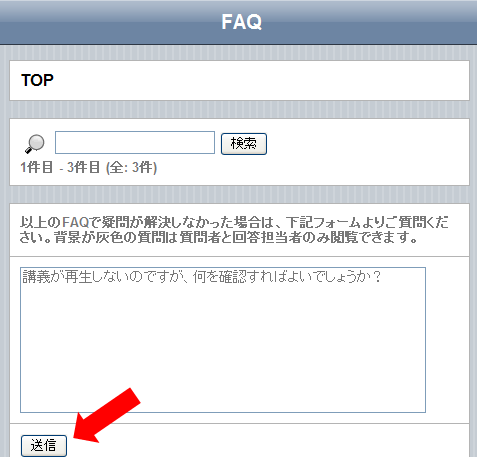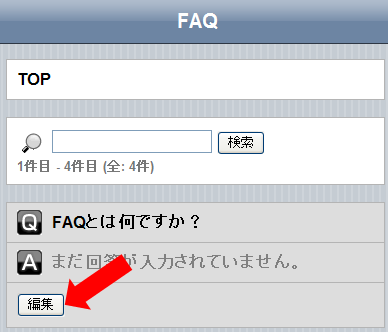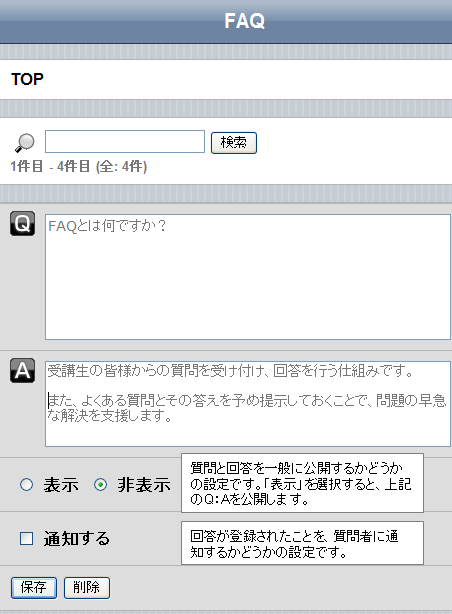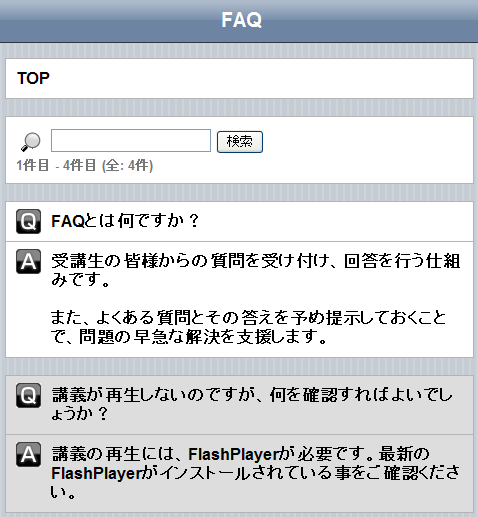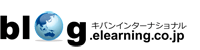特定非営利活動法人日本イーラーニングコンソシアム(eLC) が、eラーニング専門資格の基礎コース(どの専門コースをとる上でも必須です。)の「eLPベーシック」コースが開催されるとお知らせがありましたので、Blogにて紹介させていただきます。案内の内容は、下記の通り。
————————
「eLPベーシック」eラーニング・コース 【第6期】 開講のお知らせ
eLCではこの度、『eLPベーシック』eラーニング・コース【第6期】の受講申し込みを
開始いたします。
この機会に是非、多くの皆様に受講していただければ幸いです。
皆様の受講申込をお待ちいたしております。
■申込受付期間:2010年8月9日(月)~2010年8月27日(金)
■受講期間:2010年8月19日(木)~2010年10月26日(火)のうち
受講開始から最長で2ヶ月間
■受講費用:一般55,000円 eLC会員40,000円
※受講費用をお振込後、受講開始となります。
※受講開始に必要なIDとパスワードは、入金確認後にご連絡いたします。
(入金確認後5日程でお知らせいたします。(土日祝祭日を除く))
※法人でお振込いただく場合、支払条件等考慮させていただきますので
別途ご連絡ください。
■支払方法:銀行振込(申込受領後、請求書を発行します)
■eLPベーシック資格の取得について
eラーニング・コンテンツ(学習時間約13時間)を受講した後、
オンラインによる修了試験があります。
この修了試験に合格した方は、資格申請をすることで
eLPベーシック資格を取得することができます。(資格更新制:有効期間3年)
なお、「eラーニングのモラルとコンプライアンス」につきましては
最新情報を反映した教材を9月中旬より公開させていただきます。
そのため、修了試験ならびに合格後の資格申請可能時期が最短で9月20日前後となります。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
■プログラムと講師
(1)「インストラクショナルデザイン(ID)入門」(120分)
熊本大学大学院 社会文化科学研究科教授システム学専攻
教授・専攻長 鈴木克明 氏
(2)「学習心理学入門」(90分)
早稲田大学 准教授 向後千春 氏
(3)「SCORM入門」(90分)
独立行政法人メディア教育開発センター 研究開発部
教授 仲林清 氏
(4)「インターネット入門」(90分)
サイバー大学教授 JPNIC理事、APAN-JP事務局長、電子情報通信学会フェロー
小西和憲 氏
(5)「社会人教育とeラーニング」 (120分)
日本イ-ラーニングコンソシアム会長
NTTラーニングシステムズ(株)総合研修事業部企画調査室長
小松秀圀 氏
(6-1)「eラーニングプロジェクト入門」<プロジェクトマネジメント入門>(90分)
ベリングポイント(株) マネージャー 三城雄児 氏
(6-2)「eラーニングプロジェクト入門」<eラーニングプロジェクトの基礎>(60分)
エル・ピー・ティー コンサルティング合資会社 代表 秦隆博 氏
(7)「eラーニングのモラルとコンプライアンス」(120分)
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 ACCS 専務理事 事務局長
久保田裕 氏
※当eラーニング・コンテンツは、2007年11月16日(金)・22日(木)の
2日間にわたって開催した「第1回 eLP資格認定コース【eLPベーシック】
集中セミナー」集合研修の内容をライブ収録したもので、講師の所属は講演当時のものです。
■ 詳細とお申込は、下記URLよりお願いいたします。
http://elc.infodnn.com/tabid/265/Default.aspx